税理士松尾ブログ
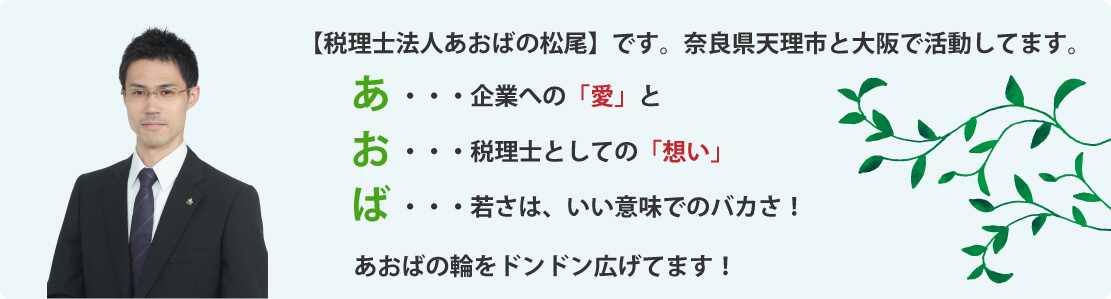
ホールディング化が事業承継に使える理由
2024-05-13
テーマ:事業承継
連休中、
・昨年11月に帝国データバンクから公表された調査レポート
・先月、日本商工会議所から公表された事業承継に関する実態アンケート
に目を通しました。
事業承継において、内部昇格によるケースがはじめて親族内承継を上回ったようです。
内部昇格のケースのほとんどは親族外承継であり、さらにM&Aのケースを加えると、過半数が既に親族外承継になっていることになります。
実際、弊社でお手伝いをさせて頂くケースでは、そのほとんどは親から子、といったような親族内承継です。
しかし、先ほどのレポートやアンケートからは、その親族内承継がほとんどを占める現状に変化の兆しが見て取れます。
商工会議所アンケートの10ページにあるように、いまの経営者自身が親族外であるという比率が、その経営者が就任して10年以内の場合に3倍近くに跳ね上がることから、外部承継がここ数年のうちに急増しているということであり、少子化の中にあっては尚更その傾向は強まるものと考えられます。
そんな状況下、長期的な視野から承継をスムーズに進める対応策として考えているのがホールディング化です。
株の承継者は創業家、事業の承継者は(第三者も含めて)門戸を広く、として所有と経営を分ける点に大きな特徴があります。
また、複数の事業を展開する場合や、事業会社が賃貸物件を所有(オーナー家由来の不動産がある)しているケースにも、ホールディング化は非常に親和性が高くなります。
弊社でも導入事例が少しづつ増え、ノウハウも蓄積されてきました。
実際、弊社(税理士法人あおば)自身が第三者への親族外承継でバトンを繋いできており、税理士法の制約から税理士業はホールディング化はできませんが、もし出来るとすれば私もやっていると思うのです。
基本的にホールディング化するために資金拠出は必要なく、反対に、所有(株主)と経営(社長)を別にするからこそ、ホールディング会社(親会社)における、創業家による憲章や経営理念の重要性が際立つようになります。
創業者や創業家の歴史そのものがそのホールディンググループにおける強烈な個性であり、その絶対性こそが重要です。
事業承継における大きなテーマとして「後継者を誰にするか?」のほかにもう一つ、「税務上の株価」がありますが、ホールディング化することで結果として株価の上昇スピードを抑える効果も期待できます。
歴史をたどれば、ホールディング会社(持ち株会社)は、戦後において解体され設立が禁止されていたものですが、平成に入ってその設立が解禁され、その流れを汲んで税務上も組織再編コスト(再編時の課税)が大幅に軽減され今に至ります。
導入の環境が整い、実際に弊社お客様、すなわち地方の中小企業者においても導入事例が増える中、中小企業で導入した場合に起きてはならない事態(リスク)は何か?
それは親会社と子会社が霧散すること、ではないかと思います。
ホールディング化が進めば、
・親会社の経営陣は創業家
・子会社(事業会社)の経営陣は第三者
という形態になる可能性がより高くなります。
しかしそれが理由に何らかのきっかけでグループが霧散してしまうことも充分に考えられます。
ホールディング化により経営陣に第三者が入ることになりますが、一方で、日本においては長寿企業が多い要因の一つに、同族企業・ファミリー企業が多いことがその秘訣にあります。
したがって、
・ホールディング化により、これからの舵取り役を第三者も含めて幅広く募り、経営を守ることのできる態勢
・一方でファミリー企業としての絶対的な理念や歴史
という両者の利点を組み合わせることがむしろ必須であると思います。
よって、
・親会社においてはグループ経営理念や創業家の歴史の共有
・事業会社である子会社の資産負債は事業に直接関係のあるものに集約する
ということが重要と考えています。
事業承継関係のセミナーでも必ず申し上げることですが、事業承継は百社百様、オーダーメイドでしか解決しません。
ホールディング化はあくまで手段ですので、オーダーメイド策を考慮する際は、
1,今後どのように経営していくか?
2,ホールディング化のメリットデメリット
の順番が逆転することのないよう念には念を入れた上で、さまざまな選択肢を模索していく必要があります。
そんな弊社も第三者承継を経て20年。
お客様と提携業者様向けにイベントを企画しています。
9/6。
奈良県コンベンションセンターで講演会のあとは隣のJWマリオットホテルで懇親会。
士業や社員も増えておりますので、改めてお披露目を出来ればと思います。
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (3)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (4)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (5)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (7)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (9)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (2)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (3)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (3)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (4)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (8)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (11)
- 2019年2月 (8)
- 2019年1月 (8)
- 2018年12月 (10)
- 2018年11月 (8)
- 2018年10月 (9)
- 2018年9月 (9)
- 2018年8月 (7)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)

 1
1