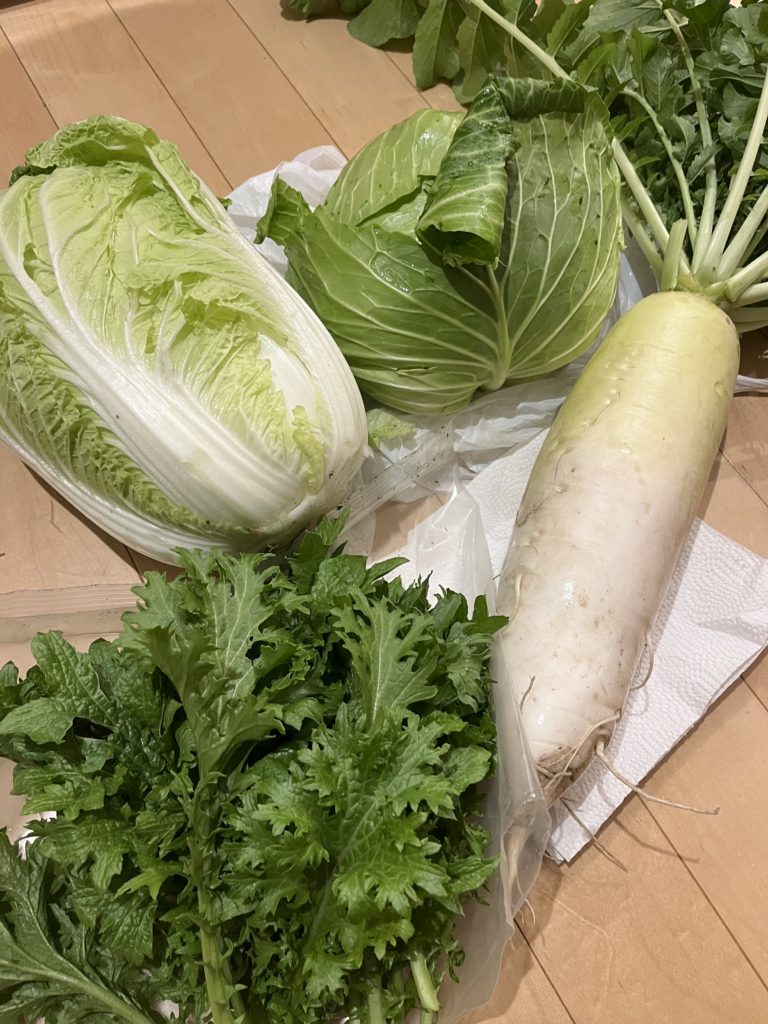BLOG代表税理士 松尾ブログ

さて、税制改正。
2022-12-13
防衛費の財源を巡り、ため息の出るような増税議論が続いており、防衛費の不足分を「法人税」を柱に確保する方向性のようです。
確かに、国際的な状況としては「ミニマム法人税」ということで、これまで法人税を出来るだけ引き下げて企業誘致など競い合ってきたところ、法人税率の下限を設ける国際的な合意がされており、その意味では法人への課税強化を打ち出しやすい状況にはあります。
参考記事:法人最低税率15%、法整備へ 国際合意受け政府・与党
さらに、コロナ前は人々が「移動」をものともせずに国境を行き交い、ビジネスにおいても地球を半周するような長距離移動も定着し、世界が一つに同質化するような状況でした。
それがコロナ禍と戦争により一気に国境という概念が蘇り、まずは各国とも国内内需を復活させた上で、内需で賄えない資源(天然資源や半導体のような高付加価値品)を融通し合う流れにあるように思います。
その状況下ではどうしても「法人の内部留保」と「富裕層」に負担を求めてしまうのでしょう。
であるならば防衛費とは別の論点のはずですが、、、。
今年の税制改正は法人税のみならず相続税の課税強化も話題に上っており、多数の改正点が浮かび上がりそうです。(12月15日に公表予定)
雇用の大半を担う中小企業にとって負担増となる改正とならぬよう見届けるのはもちろん、
企業としては、
・特別償却のような政策的な措置を有効活用した所得の圧縮
・積立型の企業保険のようにキャッシュと利益がズレる要因をつくらない
・人的資源との価値観の共有
・適切、適時の情報開示による資金調達環境
このあたりが大切になってくるのではないでしょうか。
私からも、税制のみならず、「働き方改革やスタートアップ支援(裏を返せば既存企業の撤退やむなしの認識か?)」の状況を見るに、「これからは中小企業には厳しい時代が続く」、「しかし奇をてらわず求められる価値を考えて基本に忠実に」と社内で共有したところです。
年末の公表をふまえ、
2月2日(場所:天理本店)
2月3日(場所:奈良県コンベンションセンター)
の夕刻に税制改正セミナーを企画しておりますので定員等は改めてご連絡申し上げます。
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (2)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (4)
- 2025年5月 (2)
- 2025年3月 (2)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (3)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (4)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (5)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (7)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (9)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (2)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (3)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (3)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (4)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (8)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (11)
- 2019年2月 (8)
- 2019年1月 (8)
- 2018年12月 (10)
- 2018年11月 (8)
- 2018年10月 (9)
- 2018年9月 (9)
- 2018年8月 (7)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)




 0
0