BLOG代表税理士 松尾ブログ

ワンストップで親切。相談してよかった。
2019-05-01
テーマ:税理士@松尾
私たちには律義と言っていいほど春夏秋冬が周期を繰り返して訪れます。
4つの異なる季節と季節との間(スキマ)には古傷が疼いたりと普段とは違うことが起こるため、それを「節目」として大切にしてきました。
天理市に陵墓がある崇神天皇の御代に、それまで宮中で祀られていた天照大神を皇居の外に遷し、思想や信仰の対象をあえて分散し、そこにもまたスキマを生みました。
そういった季節や思想のスキマを「優しさ」とか「思いやり」でもって埋めて新たな価値を創り出そうとする行為を絶え間なく漆塗りのように繰り返し、素晴らしい文化を育んできたのが私たちの暮らす地域であろうと思います。
そして思えば事業もまた、「スキマを埋める」行動であろうと思います。
まだまだ社会には満たされていないスキマがあって、そこにビジネスチャンスが生まれ、投資をし、回収をする。事業とはその繰り返しなんでしょうし、その行為のことを「変化」というのであろうと思います。
新元号となるにあたり、わが国最初の元号は「大化」であるらしく、日本人というのはその昔から「変化」を志向してきたのだなと勝手に解釈し、勝手に感心していた次第です。
トンネルを掘る工事は、「基準点」を常に大切にすると教えて頂いたことがあります。
トンネルを掘り始める最初の地点を「基準点」と定め、掘り進む都度、常に基準点に立ち返り、基準点からどれくらい進んだかを常に確認しながら作業を遂行するそうです。
同じように私たち個人や企業にも基準点や原点があるはずで、その原点に立脚した強みや固有技術があるはずです。
「強みのない企業なんてない。でも強みは一つしかない。」と言われます。
選挙、消費増税、人手不足。さまざまな変化が訪れますが、基準点に立脚した自らの強みでもって社会のスキマを埋める経営努力を続けていかなければなりません。
私どもも、セミナー等による情報発信、海外を含む様々な士業との連携、チャート式決算書のご提供をはじめとし、昨年からは国家的な課題である「事業承継」にも注力してまいりました。
ただでさえ後回しになりがちなテーマですので私どももできるだけ早い時期からの本質的価値のあるご提案を心がけているところです。
しかしながら一方で世間には様々な情報が溢れかえり、全体的な考察を加えることなく、贈与税が100%猶予される納税猶予制度の単発的な情報だけが独り歩きしてしまっている感覚もございます。
事業承継の時期に差し掛かる企業様に限らず、ぜひとも原点や強みを共有させて頂き、ともに継続発展の道を歩んでいければと考えております。
とにかく地域経済の根幹である雇用を支える中小企業の皆さまに「安心」を。
ワンストップで親切。相談してよかった。
そのお言葉の積み重ねをしていけるよう、今後も研鑽を重ねていこうと思います。
考えることと行動すること
2019-03-29
テーマ:税理士@松尾
2月は確定申告の時期にもかかわらず
「価値の輸出のためのシンガポールツアー」を企画し、
⇒詳細
戻ってからは
社員のご実家から頂いたトマトで栄養補給しつつ
確定申告時期も終了。
申告期限の翌日には、
恐れ多くもご縁を頂戴し、
市民プロジェクト会議なるものに参加をさせて頂いておりました。
色々なお立場の市民
教育関係者
行政関係者
などが集まって、ざっくばらんに話し合いをするものです。
この日は
「10年後の天理」がテーマ。
スパンが長すぎてどうしても抽象的になりますが、
その点はまずはブレーンストーミング形式で意見を出し合い
付箋紙に書いて書き出してジャンル分けし、
デザイナーさんがイラストにしてまとめる、
という手法により出来るだけ分かりやすく可視化する試みをされていました。
個人的には、
・地方の活性化は「雇用」「教育」の2本柱
・雇用は地場の中小企業こそが担い手であってほしい(その財務面のサポートは税理士)
・教育環境は教育関係者だけに頼ることなく、
経営者やリタイア後の市民などが全員参加で子供たちとの接点機会をもっと増やしては?
・そのために体験型イベントやコンサートや講演会など、入り口として「楽しい」イベントが大切
(そんな思いで昨年末には「しめ縄づくり体験会」を開催しました)
・交流イベントに無駄なものなんてない
・人生はみんなそれぞれだからそれぞれに価値があって、それを子供たちに伝えるだけですごい教育効果がある
勝手気ままに、青年会議所活動での学びや普段から考えていることを意見させて頂きました。
人生は「考えること」と「行動すること」からできていると言いますし、
行動が大切。
結局、最後は「何をやるか」ではなく「誰がやるか」。
無駄なことなんてないのだから。
というわけでこれから「教育事業」として取り組むこととなった
「日本定例研究会奈良」
⇒詳細
自分自身、
4月は「基礎」を見つめなおす月となりそうです。
日本の基礎「日本定例研究会奈良」
⇒詳細
会社の基礎「株主戦略セミナー」
⇒詳細
これからいよいよ人口が減り、
GDPの根幹である「消費」が目減りする中、
天然資源に乏しい日本日本経済のカギを握る、
「価値の輸出」の成功例としてこんなニュースがありましたね。
例えば
・奈良にフォーカスした旅のパッケージを現地(海外)で販売する
例えば
・現地飲食店のメニュー品質向上とシェフのトレーニングは日本側、店舗管理は現地が担当してのコラボ
例えば
・シンプルにインバウンド
こういった日本以外からお金を払ってもらう、という意味での「価値の輸出」
は信頼できるネットワークがあれば中小企業ででもできることです。
先日のシンガポールツアーはそのための「出会い」のツアーでした。
今は人手不足で忙しくても、
大企業だけではなく中小企業も、
さらにいうなれば地方の中小企業も、
その価値を輸出する視点を持つだけで「今」への取り組みが随分と変わります。
その上で
利益を出し、
雇用を守り、
地域経済を元気にする。
そんな取り組みと気付きの提供を今後も続けていければと思っています。
士気高く、自信にあふれ、みな信じあう組織
2019-02-17
テーマ:税理士@松尾
日曜日。
前日の晩から家でゆっくりとくつろがせて頂きました。
(これ、1月に書いてます。)
昔読んだ本を読み返したり、
YouTubeでラグビーを観戦したり、
冬の日差しを感じながら散歩したり、
それでも時間を持て余し、、、
今では我が家のリビングから姿を消して
いちばん端っこの小さな部屋に追いやられたテレビのスイッチをつける。
まずはCMの多さに辟易し、
何よりも、何かにつけて「平成最後の」というフレーズの多さに違和感を感じ、
30分も持たずにスイッチoff。
なにかのブログにも同じようなことが書かれていて、
【事にふれて平成最後と報道されることに
心が痛む】と書かれてあったのが
強く印象に残っています。
リーダーは
自分のやりたいことを中心に据えるのではなく
自分がやるべきことを中心に据えます。
そのことを何年も、何年もの時間をかけて考え抜かれた結果である「平成の終わり」という事象。
災害。
ジャパンアズナンバーワン。
一人あたりGDPやODA世界一からの転落。
そしてインターネット。
平成もまた、激動の時代。
日本の国じたいが承継を迎える時期に、
「経営のパートナーとして安心を提供する」ミッションに取り組もう、
そして
士気高く、自信にあふれ、みな信じあい、取るべき行動をとり、態勢の整った、
そんな組織にちょっとでも近づけよう、と思いを巡らせました。
個と和の関係性から源流を思う。
2019-01-20
テーマ:税理士@松尾
日本全国にある神社の数は8万を超え、実はコンビニよりも圧倒的に多い数を誇ります。
奈良県天理市の南端、柳本町には第10代崇神天皇の陵墓があります。

私が子供のころから慣れ親しんだ場所でもあります。
実は崇神天皇の時代に疫病が大流行し、豪族間の争いにより国が大いに乱れていたといいます。
そこでそれまで皇居内に祀られていた天照大神と大国魂神を皇居の外に移され、
各地に神々が祀られる社を定められました。
このことが神社が私たちの生活に深く根差す契機になったといわれています。
実に2000年以上も前のこと。
私たちの何気ない生活に流れる大きな源流を今に感じざるを得ません。
さらには、皇居内に祀られていた偉大なる神を外に祀り、
天照大神
大国魂神
そして天皇
という3つの偉大なる力をあえて1つに集中させず、
3つの和としてその間に物理的・精神的な空間をあえてつくったことで、
統一された大和の力が全国へと波及していったそうです。
企業も、家庭も、まずは個の力を強めるのも大切ではありますが、
それらが「和」として調和しあうことこそが全体をさらに強くするのかもしれません。
個人が個として、まずはなくてはならない存在となり、
それぞれの個性が集まり和として新たな価値を生み出す。
それもまた私たちの源流なのだと思います。
(一社)フライトってなんの会社、と良く聞かれますが。。
2019-01-16
私の名刺。
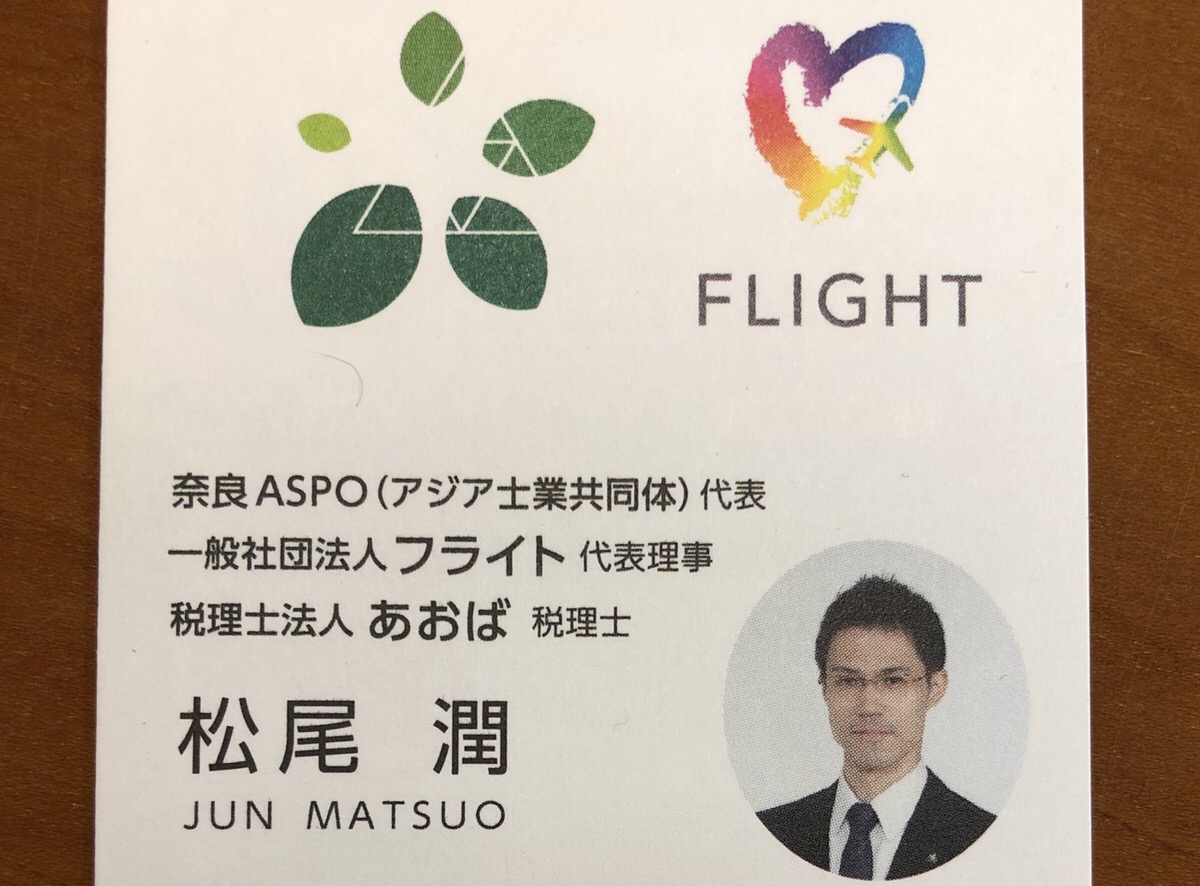
フライトって何の会社?
と良く聞かれます。
平たく申し上げると「セカンドオピニオン」の会社です。
他にはこんなツアーの企画をしたり。⇒シンガポールツアー
セミナーの企画をしたり。
セカンドオピニオンの場合は、
税理士さんは他に頼んでるけど、
・お年を召していて連絡を取りにくい
・父親の代からの付き合いなので今さら変えられない
・情報提供がない
・提案がない
・質問しても返事が遅い
・でも経営の「これってどう思う?」って質問を気軽に聞けるプロが欲しい。
・自社の「弱点」を客観的に伝えてほしい。
そんな時にお使いを頂いています。
セカンドオピニオンを経て、
税理士の契約に変更して頂けるときもあるし、そのまま期間満了で終わるときも、
何年もセカンドオピニオンをお使いいただいているときも、さまざま。
現在3社さまにご活用して頂いています。
税務顧問をさせて頂いているお客様がいらっしゃる中で、
セカンドオピニオンのお客様も全て松尾個人が対応しているので、あまり件数対応はできませんが、
現在2社分の空きがございます。
契約の時に直接お会いさせて頂き、
それ以降は基本LINE・Chatwork・Messengerで、という場合は月額2万円でお使いいただけます。
もちろん必要に応じてその後、お会いもさせて頂きます。
「フライト」の名前の由来は、「経営」を飛行機のフライトにたとえて、
目的地に着いたときに「こんなところに着くはずじゃなかった!」となってからでは遅いので、
目的地を見据えて一緒に飛んでいきましょ!
ってところからきています。
1年契約ですのでお気軽に。
シンガポールツアーは今日が締め切りです!
2019-01-07
奈良の若手経営者向けシンガポールツアーは
今日(1/7)が締め切りです。


特に、日本は人口が減るからこれからは海外だ~っと
何が何でも海外進出を勧めたいわけではありません。
わたし自身、税理士という仕事は日本の税法を扱う職業なので、
海外は関係ない、と言えばないのです。
それでも経験として、海外との接点があることで
・解決できる課題が増え
・ご提供できる「気付き」の幅が増え
ていることも事実です。
「紹介」というビジネスにおける最強のフィルターを通じ、
いちど海外の人間と日本の人間とがリアルに接点をつくってつながれば、
あとは日本にいながらでも海外活用は可能です。
地方にいながらでも、世界中からリアルな情報を入手できます。
その情報に、
「どんな」情報か、にプラスして
「誰からの」情報か、という価値が加わります。
また反対に、地方にいながらでも世界中に情報やノウハウを発信できます。
ちなみに今回のコンテンツは、
どこかのコンサルさんや金融機関が用意したものではなく、
2年前の出会いと
士業の集まりであるASPO(アジア士業共同体)のネットワークを活用してのものです。
実は一番リスクが高く、海外活用の最終形ともいえる海外進出。
そこに重きを置いているわけではないので、
「教育・介護・経済(金融)」という大きな間口から「違い」を知るツアーです。
これからの日本は特に、
ビジネスをする上でこの3分野との接点からは避けて通れませんもんね。(あとは農業と)
日本の「当たり前」を疑うツアーにしたいと思っています。
「価値」は「違い」から生まれますので。
エラそうに言う私も英語はしゃべれません。海外生活もしてません。
ただ、シンガポールでの出会いを楽しみながら接点を構築し、
社業に活かすつもりです。
さらに詳細⇒http://flight.or.jp/recent-article-seminar/seminar-article%E2%85%A1/
税理士松尾より新年のご挨拶
2019-01-02
テーマ:税理士@松尾
明けましておめでとうございます。
紙の新聞は買わなくなってしまったのですが、
元旦は日経新聞をコンビニで買うようにしています。
元旦のトップ記事くらいは…ということで。
2015‥
変えるのはあなた
2016‥
目覚める40億人の力(インド俊英)
2017‥
「当たり前」もうない
2018…
溶けゆく境界
でした。
そして2019年は…
【つながる100億の脳】
人体最後のフロンティアである脳。
脳は人間が人間であるゆえん。
その潜在能力が解き放たれようとしている。
その時に社会や人間のあり方が問われる。
今までの30年の進化とこれからの30年の進化はスピードが全く違う。
脳と脳が繋がれば言語さえ不要。
2050年にはAIは人間の知性を超える。
脳の潜在能力が解き放たれた時にこそ自分自身が何者か、考えることが大切。
というような内容でした。
あなたは何ができる人なんですか?
あなたの信じるものはなんですか?
根源的な問いに答えられる価値観と、
相手との違いを受け容れる価値観とが
大事になってくるのだと思います。
価値観教育が会社に求められるのだと思います。
昨年ホームページをリニューアルし、まだまだ試行錯誤ではありますが、
今年もスタッフブログ、松尾ブログ、ともども宜しくお願い致します。
今年最後のブログです。
2018-12-28
テーマ:税理士@松尾
12月22日は、長らくお世話になった
天理青年会議所の最終理事会。
これで私の役目も終わり。

12月23日は
青年会議所で得た気付きを実践し続けるために立ち上げた
「STAGE」の第一弾事業。
「お正月講座+しめ縄づくりワークショップ」
石上神宮の拝殿(国宝)での正式参拝から始まり、


そのまま拝殿で、
権禰宜からの石上神宮の由緒をお聞かせ頂き、

一般社団法人国際教養振興協会の代表理事である
東條英利様からのお正月講座。
・お正月
・門松
・しめ縄
・年神さま
・おとしだま
・初詣
・おせち
・祝日と祭日の違い
などなど日本人にとっての「当たり前」に向き合う機会に。
そして今、
しめ縄自体の意味を分からずに飾る家庭も多くなるだけではなく、
実は市販のしめ縄は「日本の稲わら」ではなく「中国の水草(雑草の類)」であることも多い
現状を打破すべく、
岐阜県東白川村の国産の稲わらを使ったしめ縄づくりワークショップ。
穂が実る前に刈り取り、しめ縄用として厳重に保管してきたものです。
まだ青々としていて何より香りが素晴らしかった。

老若男女、35名で実際にしめ縄をつくりました。

できたしめ縄は当然、各家庭にお持ち帰り頂きました。

12月10日に広報を開始して
12月23日の事業。
そもそも案内が急。
クリスマス一色。
年末。
連休の中日。
不利な条件がそろってしまう中でも、
「こんなんやるから来て~」
で来て下さった皆様に本当に感謝。



有難いお言葉を頂戴するも、
それをそのままお返しします。
感謝を接着剤に、
これからも人の輪が広がることを切に願います。
人間はその漢字の通り、人の間(あいだ)でいきていますもんね。
仕事、食事、Facebook。。。
形はいろいろあれど、接点を持っていただいた皆様に感謝申し上げます。

医者と税理士は若い方がいい(H30とH31の税制改正大綱を読み比べてみる2/2)
2018-12-23
毎年公表される税制改正大綱には、
その最後に
次年度以降も引き続き検討する項目が列挙されます。
・H30税制改正における引継ぎ事項
・H31税制改正における引継ぎ事項
を比較してみると、
・実現した項目
・再度引き継がれた項目
・新しく引継ぎとして出てきた項目
が良く分かります。
前回のH30税制改正において「検討事項」として挙がっていた項目を早速みてみます。
1,年金課税
年金制度改革の方向性も踏まえ、課税のあり方を引き続き検討する
⇒H31も同様に引継ぎ
2,金融所得課税の一体化
投資家が多様な商品に投資しやすい環境を整備する視点から引き続き検討する
⇒H31も同様に引継ぎ
3,小規模企業に係る税制のあり方
個人と法人成り企業に対するバランスを図るための外国の制度も参考に、
控除のあり方を全体として見直すことも含め、所得税・法人税を通じて総合的に検討する
⇒H31も同様に引継ぎ
4,子供の貧困への対応
ひとり親に対する税制上の対応について平成31年度税制改正において検討し結論を得る
⇒これ、今回公明党さんが最後まで主張していたやつですね。
実は昨年から引き継がれていたのが分かります。
今回(H31)でも住民税の非課税枠が拡大されたものの、
「H32税制改正において検討し、結論を得る」となりました。
5,個人事業者の事業承継
その承継の円滑化を支援し代替わりを促進するための枠組みが必要
⇒H31税制改正において対応されました。
事業用の土地建物に係る相続税・贈与税の納税を猶予するというもの。
したがってH31税制改正大綱における「検討事項」からは消えています。
6,医療に係る消費税のあり方
医療機関の仕入れ時の消費税負担等に配慮し、H31税制改正で検討、結論を得る
⇒今回(H31)で、診療報酬の配転方法の精緻化、医療関係器具の特別償却制度の拡大といった
措置が取られました。
したがってH31税制改正大綱における「検討事項」からは消えています。
7,国境をこえたサービス提供に対する消費税の課税のあり方
課税の対象とすべき取引の範囲及び適正な課税を実現するための方策について引き続き検討
⇒こちらは今回(H31)では、経済の国際化・電子化への課税上の対応は適正な課税を確保するための方策について引き続き検討を行う、と表現されました。
8,原料用石油製品等・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
9,事業税における医療関係サービスへの軽減税率等・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
10,電気供給業等への外形標準課税・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
11,ゴルフ場利用税のあり方・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
12,民法における成年年齢の引き下げに伴う、税制上の年齢要件
民法に合わせて18歳に引き下げることを基本として検討をおこない、結論を得る
⇒こちらは相続時精算課税制度の適用年齢・NISAの適用開始年齢の引き下げなどで
対応されています。
今回(H31)では検討事項に挙がっていません。
で、H31で新しく「検討事項」で上がってきたものは。。。ひとつ。
自動車関係諸税について
自動車を取り巻く環境変化の動向等を踏まえ、その課税のあり方について中長期的な視野で検討をおこなう。
と新しく記載されました。
巨大産業、自動車産業をめぐっては今年も様々な動きがありました。
トヨタ自動車とソフトバンクとの連携。
カルロスゴーンの逮捕。
「クルマ」の枠組みをこえ、「移動手段」として新たな時代の到来を予見しての一文でしょうか。
参考記事:https://www.businessinsider.jp/post-180756
いずれにしても、
「検討事項」として
・新たに出てきた項目が少ないこと
・来年以降も同様に引き継がれている項目が多いこと
から、今後は何か目新しいものが登場するよりも
既存の税制(特に事業承継税制)にマイナーチェンジが
繰り返されるような気がします。
実務的には、その「マイナーチェンジ」へのキャッチアップが大変ですし、
選挙イヤーの来年の結果次第ではまた目新しいものが出るかもしれません。
ある経営者は言いました。
「医者と税理士は若い方がいい」
それだけ目まぐるしく変わるという意味だそうですが、
その期待を裏切らないように頑張ります。
H31とH30の税制改正大綱を読み比べてみる1/2
2018-12-19
毎年12月中旬に税制改正の大綱が発表されます。
H31年度分は先日公表されました。
ページ数にすると100ページを優に超えるほどの量がありますが、
たいていの場合、
大きな構成は次のようになっています。
①基本的考え方
②具体的内容
③検討事項
一番ボリュームが多いのはいうまでもなく②の具体的内容ですので、
こちらは税制改正セミナー(2019年2月1日 @天理市民会館)
でご説明するとして、
2年分の①と③を「比較」して読み比べると税制改正の「傾向」が見えてきます。
平成30年度の税制改正大綱と
平成31年度の税制改正大綱
それぞれの「基本的考え方」と「検討事項」を読み比べるわけです。
まずは「基本的考え方」。
税制改正が実現した項目の「背景」を述べる部分です。
だいたい15ページくらい。
平成30年度税制改正
<一段落目>
雇用・所得環境は大きく改善している
<二段落目>
デフレ脱却を確実なものとしていく必要がある
誰もが生きがいを感じられる一億総活躍社会を作り上げる必要がある
⇒概論といいますか、コンセプトを述べています。
<三段落目>
働き方改革を後押しするために個人所得課税における諸控除の見直しを図る
⇒昨年、実際に実現した項目です。
で、平成31年度税制改正
<一段落目>
雇用・所得環境は大きく改善している
⇒昨年と同じことを言っているのが分かります。
<二段落目>
消費税率10%への引上げを平成31年10月に確実に実施する。
⇒昨年はこの時点でもコンセプトを述べるにとどまっていましたが、
今年はいきなり消費税のことが出てきました。
決意のほどでしょうか。
<三段落目>
企業経営者がマインドを変え、投資拡大などに積極的に取り組むことを期待する。
前回の消費税率上げの経験を踏まえ、需要変動の平準化にむけてあらゆる手立てを尽くす。
⇒こちらもまあ、消費税税率アップありきの文章ですね。
(ちなみに四段落目も軽減税率のことですので、消費税最前面押しの様相です。)
というわけで、メインは消費税率アップによる需要減対策ということになるのかもしれません。
比較をしながら、こういった「背景」と「傾向」を念頭に読み進めていくこととするのですが、
当然、消費税関係以外の項目も出てきます。
これらは、昨年の税制改正大綱の「③(今後の)検討事項」に挙がっていた項目
であることが多く、
やはり単年でのみ読むのではなく「比較」の要素を取り入れることで
見える視野が広くなります。
財務も同じですね。
その年だけの損益計算書、貸借対照表のみをみるのではなく、
前年のそれらと比較することで経営に欠かせない気付きが得られます。
次回は税制改正大綱における「検討事項」を比較してみることとします。
青年会議所、奈良県全体での卒業式
2018-12-07
テーマ:税理士@松尾
30歳で天理に戻り、
ほどなくして入会をさせて頂いた青年会議所。
40歳の節目を迎え、青年会議所から卒業。
この日は
奈良県9つある、全体での青年会議所の卒業式でした。
そして光栄にも、
卒業生を代表して「答辞」としてスピーチをさせて頂きました。

いわゆる青年団体には「商工会」や「商工会議所」もあります。
私も商工会の会員でもあるのですが、
それらと青年会議所との決定的な違いは「存在理由」にあります。
商工会には商工会法。
商工会議所には商工会議所法。
法律が存在理由になっており、いわば絶対になくならない。
一方で青年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という「目的」のみが存在理由。
「社会を少しでも明るく、豊かな社会にしたい」という「想い」のみが存在理由。
「想い」がなくなれば組織もなくなる、
いわば「終わりがある」という点が決定的な違いです。
私たちは「終わりがある」と聞くと少しマイナスのイメージを持ちがちですが、
実は反対で、
終わりがあるからこそ「今」が、「存在」そのものが、輝くのです。
人間と同じ。
人間もいつか死ぬからこそ「今、生きていること」が輝くのです。
「生きている」こと自体に価値が生まれるのです。
不老不死だったら時間はたっぷりあるので、「今」のほほんと生きていればいいのですから。
そんな、存在していること自体が価値を持つ「青年会議所」を卒業してからは
理事長の職をお預かりしたときのスローガンである「価値を語る」をライフワーク
にしていこうと思っています。
税理士法人あおばでは採用活動も積極的にしているのですが、
先日面接に来られた方からは、面接を通じて「税理士のあり方を学ばせて頂きました」
とお礼を言われました。。。
JCの価値を語る
税理士の価値を語る
中小企業の価値を語る
事業承継の価値を語る
語ることは最も人を動かし、費用もかかりません。
語るためには・・・信じることです。
全ては信じることから始まります。
だからこそ
地域経済を支える中小企業にたいする、税理士業を通じたお役立ちを信じているのです。
先日は奈良県全体での青年会議所の卒業式でしたが、
週末はいよいよ所属する「天理青年会議所」の卒業式。
これが最後。
めっちゃくちゃ寂しい。
でも、
青年会議所の後輩たちがこの地で想いをつないでくれることを信じ、臨みます。

しめ縄を自力でつくって思ったこと。
2018-12-03
テーマ:税理士@松尾
当たり前すぎて何とも思わないこと。
当たり前すぎて意味を理解しようと思わないこと。
「当たり前」の対義語は「有難う」と言いますが、
有難うと思うためにはまず「向き合うこと」から始めなければなりません。
なぜなら、当たり前と思うことは当たり前すぎて、向き合おうとすらしないからです。
向き合ってはじめて
当たり前から
感謝が芽生え、
感謝から誇りが芽生え、
誇りをもつことで品位が芽生えます。
だから大切なのはまずは「向き合うこと」だと思うのです。
年末を控えるこの時期、
誰もが「当たり前」に過ごす代表格が「お正月」だと思います。
お正月って何のためにするの?
寝正月の本当の意味は?
門松って何のためにあるの?
お年玉って何のためにするの?
そして「しめ縄」ってどういう意味があるの?
こういう当たり前すぎて向き合おうとしないことを
改めて勉強しに、名古屋まで行ってきました。
題して「しめ縄づくりプロジェクト」
で、自力で稲わらで作ったしめ縄がこちら。

まー形はともかく、
年神さまをお迎えするときの「入り口」を示すしめ縄を、
お正月の意味を勉強したうえで実際に作ると
格別のものがありました。
で、同時に思ったのは、
実は古来よりの文化は、
崩壊しかかっているのではなく、
すでに崩壊していたのではないか、ということ。
何かの責任感から古来の文化を次代につなげなければならない、
と思いつつも、
意味合いを分かっていなかった時点で、
そして恐らくお正月の意味を知らない人が大多数と思われる時点で、
文化は崩壊しかかっている
というよりも
すでに崩壊していたのではないか
という想いがこみ上げてきました。
なんとしても、
崩壊を食い止めるのではなく、
もはや
復活をさせなければならない、と感じました。

天理創業スクールで【財務の価値】を発信
2018-11-11
4年連続で講師を担当させて頂いている
天理創業スクール。

創業をお考えの方
創業まもない方
後継予定者の方
20代の方
定年退職された方
年齢も性別もバラバラでありつつも、
新たな「業を興さん」とするお気持ちは一致しています。
今年は
・財務の価値
・7つの「大事」
にスポットをあてて2時間お話をさせて頂きました。
アンケートより。
「今までで一番ひきつけられたお話しでした。
何かあったらまずは松尾さんに相談しようと思うプレゼンでした。すごい。」
「財務の知識がなかったわけではないが、今日で点が線になったな~と思います。」
と身に余るお言葉を頂戴しました。
財務の価値を一言集約すると
「チェック」ということばに行き着きます。
いいか悪いかのチェック
良くなっているか悪くなっているかのチェック
キャッシュが回るかのチェック
機械を買っていいかどうかのチェック
利益がどこにいったかのチェック
利益を出すためにどこから手をつけるかのチェック
目標とのチェック
ビジョンとのチェック
愛する家族と従業員を守れるかのチェック
それらの判断をするときに必ず「財務情報」が必要です。
その価値をお伝えしたうえで、
実務上大切な7つの視点をお伝えしました。
そのあとは北海道大学アメフト部時代の同窓生と同窓会。

身も心もお腹一杯!の日でした。
山の辺の道ハイキング&ランチ
2018-11-04
テーマ:税理士@松尾
日本最古の道「山の辺の道」から望む、
二上山。

毎年、秋になると、お客様が主催される、
山の辺の道ハイキング&ランチに参加させて頂いています。
日本の原風景に触れながら、


約2時間ほどのハイキング。
愛するスタッフと。

この原風景が50年後、100年後も続くように、
地域の雇用を守る中小企業へのお役立ちをしていかなければ。
人間教育の柱としてのスポーツ
2018-10-31
テーマ:税理士@松尾
私たちの本店が所在する
「天理」。
古くから人間教育の柱としてスポーツが位置付けられてきました。
いわゆる天理スポーツ。
野球。
柔道。
ホッケー。
そしてラグビー。
先日、図書館で借りた書籍に天理ラグビーの基本10則なるものが紹介されていました。

ビジネスにそのまま当てはめられます。
移民の国、人種のるつぼ、アメリカでは、
移民の国だからこそ、
人種のるつぼだからこそ、
パトリオット教育と称して愛国教育、アメリカならではの価値観を伝えることが
徹底されていると聞きます。
一方の日本では。。。
なかなか浸透していません。
だからこそ、会社も人間形成の一つの「教育機関」としての要素が必然的に高くなります。
仕事の意義。
税理士としての仕事が持つ意義。
本当の豊かさとは。
仕事はまったく充実していないけど自分の人生が大好きな人に、
なかなか出会うことはありません。
そんな時に何げなく読んでいたときに出くわした
天理ラグビーの精神。
原点回帰。
天理な寄席
2018-10-28
月亭方正さまを地元にお呼びして、
「天理な寄席」として開催した落語会。


196名にお越し頂き、会場は満席。

テレビの芸人としてではなく
落語家としてご出演頂き、「さすが」のひとこと。
地域経済の循環には「企業誘致」が最も効果的だとは思いますが、
自発的に地域を盛り上げようとする企業や団体が存在していることも不可欠。
今後も、本業以外でも地域を盛り上げる仕掛けを継続していければと思います。
天孫降臨の地と流しそうめん
2018-10-24
テーマ:税理士@松尾
少し前のことですが、
愛する仲間たちと宮崎県は高千穂に行ってきました。

高千穂というと、言わずと知れた「天孫降臨」神話の地。
ニニギノミコトが高天原から地上に舞い降り、国づくりをはじめた地です。
仲間のうちの一人が神職なので、素朴なギモン。
「地上に降り立ったというけど、地上の、高千穂の、どこに降り立ったの?」
そう聞くと「特定されていない」とのこと。
その答えを聞いたとき、すごく日本らしいな、と思いました。
恐らく、天孫降臨の地は「ここ!」って特定してしまえば、
もっと分かりやすいし、国内・海外からの観光客も増えて
高千穂の地域経済も変わっていたのかもしれません。
以前に行ったアメリカのダラス。

ここなんて、ケネディが撃たれた場所は「ここ!」と
道路上に「×」印が書かれていて、当然のことながら観光名所となっていました。
それに比べると高千穂は、
日本の歴史の深さ、寛容さが際立つ地のような気がします。
日本列島の始まりである「オノコロ島」もありました。
オノコロ島・・・これって淡路島にもあったな、と思いつつ。汗
どちらがorどれが正しい、という二項対立ではなく、
全てを寛容に包み込み、新たな価値を生み出さんとする
日本の価値観のすばらしさを感じた旅でした。
天孫降臨の地、高千穂でなぜか「流しそうめん」。

これも新たな価値。。。なのでしょう(笑)
心ひとつに。
2018-10-21
テーマ:税理士@松尾
天理青年会議所として近畿地区大会をみごとに優勝し、
近畿地区代表として出場した全国大会。

野球経験のない私の仕事はただ一つ。
声を出すこと。。。涙
元プロ野球選手がバッテリーを組むチームに「1対2」で敗れはしましたが、
心地よいスポーツの力を感じた日。
その後は最新の中小企業の支援施策を学ぶ。

事業承継税制や再生協議会の支援策の他に、
中小企業にとって巨大なテーマである「連帯保証」についても、
代表者保証をつけない施策について学びました。
キーワードは「誠実さ」でしょう。
誠実に、業績や計画を定期的に金融機関に報告を重ね、
誠実に、経営において公私の区分を明確にし、
誠実に、不正や誤りの起こりにくい体制を構築し、
誠実に、実績を積み重ねて「経営の目的」を果たさんとする。
その積み重ねが連帯保証をなくすことにつながります。
今まであまりにも当然のように個人保証が横行し、いわば「人質」といってもいいような状態でしたが、
弊社での実務上の傾向を見渡しても確実に、
誠実な経営者は連帯保証から解放される流れになりつつあるように思います。
その後は年に一度の社員旅行。
明治の激動の空気感がただよう道後温泉。

坂の上の雲。
来島海峡。水軍。明治の要塞。
秋山兄弟。
松山城と今治城。
人が紡いできて出来上がっているこの空気感は何度来ても素晴らしい。
しまなみ海道も下から。

台風一過の澄んだ空気。

職分に必要な知識の収集を怠ることなく、
この世は人の集まりであることの原理原則を忘れることなく、
心ひとつにこれからも進んでいきます。

経営の定石
2018-10-03
決算書は、
経営におけるある一定時点での「行動の成果」を表現します。
税務署や金融機関のように、決算書が出来上がった「結果」だけを見るのではなく
決算書を一緒に作り上げる「過程」と「結果」のすべてに関与させて頂く
税理士という仕事。
経営における「行動の成果」である決算書を扱う人間であればこそ
「経営の定石(セオリー、原理原則)」を忘れてはならないと考えています。
で、
たどり着くのは「古典的名著」。
そして
それを「繰り返し定期的に読み返すこと」
公認会計士の天明茂氏の著書や村上龍氏の著書まで、
だいたい10冊ほどあるのですが、
最近響いているのはこの2冊。

初版から30年以上も経っている本ですが、
すでに、これからの時代は
・高負担時代(エネルギーコスト上昇、高齢化による社会的コスト増大)
・選別淘汰(準決勝ではなく決勝戦をむかえる)
・専門化、個性化、差別化がさらに進む
・寡占化、ナンバーワン化
・小グループによる活性化
・技術革新、設備合理化がさらに進む
・タテ型成長からヨコ型成長へ(多角化、多様化、分散化)
・地方の時代、地方への環境改善投資が進む
・旧来の惰性と安住の地場企業の淘汰
・プロ専門家、幹部の人材育成が大きなテーマ
という、十分に今でも通用することが書かれています。
もう絶版になっていると思いきや。。。
なんとアマゾンで買えます。
しかも送料よりも安い価格で。。。涙
アマゾン、すごいですね。
というわけで、ではないのですが、
この本を購入。

古くも変わらぬものと新しきもの。
ともにインプット。
また経営者の皆様とのご面談時に、
「にじみ出るように」アウトプットされることを期して。
- 2026年2月 (2)
- 2026年1月 (1)
- 2025年12月 (2)
- 2025年11月 (2)
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (2)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (4)
- 2025年5月 (2)
- 2025年3月 (2)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (3)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (4)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (5)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (7)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (9)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (2)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (3)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (3)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (4)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (8)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (11)
- 2019年2月 (8)
- 2019年1月 (8)
- 2018年12月 (10)
- 2018年11月 (8)
- 2018年10月 (9)
- 2018年9月 (9)
- 2018年8月 (7)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)


 1
1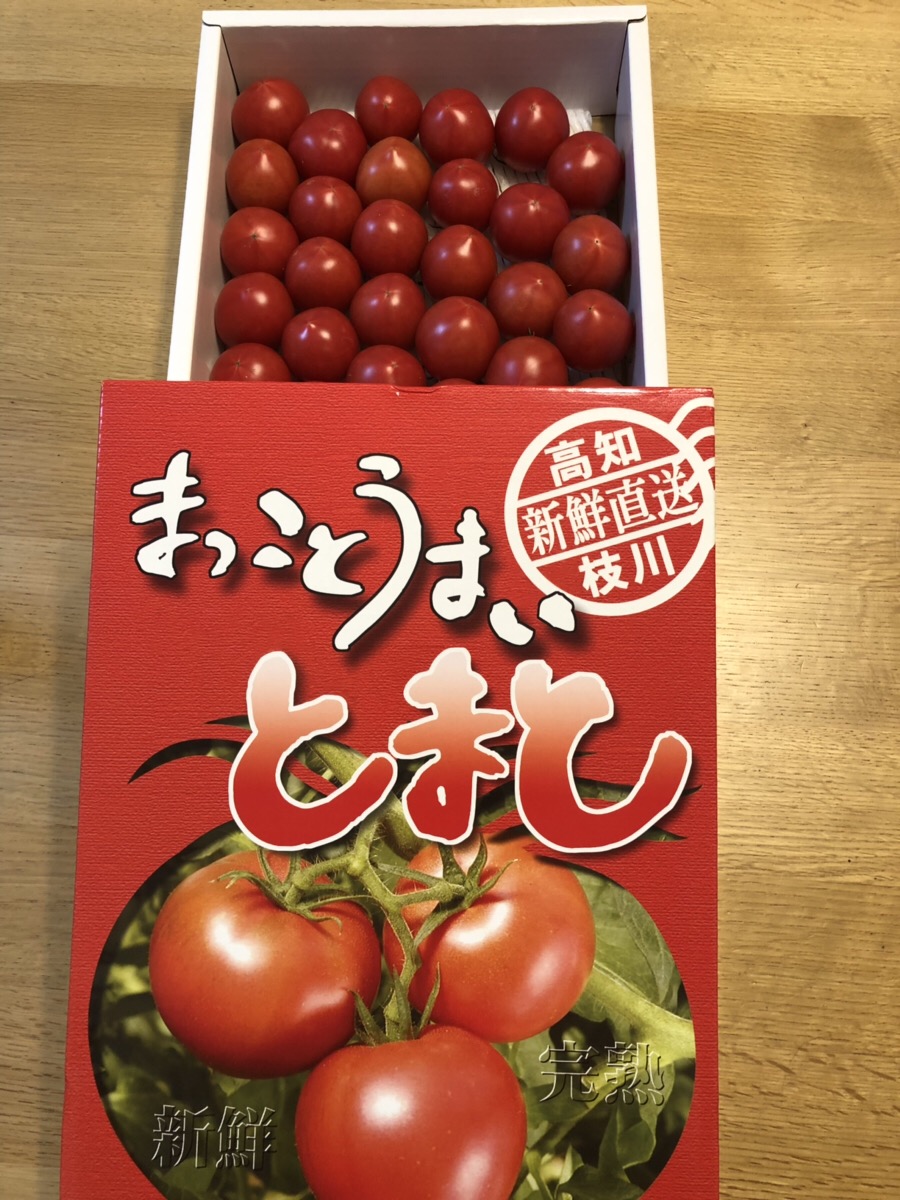




 0
0