INHERITANCE資産を守る
INHERITANCE相続業務
あなたの財産を守る
お手伝いをします

相続業務における
3つの特徴
1.継続的な対応
相続税の申告、贈与税の申告、相続対策等、業務を通じて弊社と御縁を頂いたお客様に対しては、有償・無償に係わらず、継続した対応を心がけています。 特に、相続関係業務における対応は、算定した評価時点の評価額や、家族構成の変化、社会的・経済的状況、税制改正等により、大きく変動します。 車や家電製品を買った後にアフターサービスがあるように、我々税務サービスにおいても、継続的に広報誌・セミナーや個別対応を通して、その時代・状況に対応したベストな対策・提案をその都度変更して提案します。 決して、その場限りの申告・提案は行いません!
2.ワンストップ・サービス
相続業務にかかわる申告・提案はさまざまなノウハウや知識が必要です。我々税理士法人あおばは、数多くの実績と経験により、多種多様な専門家集団のネットワーク(弁護士・不動産鑑定士・司法書士・土地家屋調査士・一級建築士・FP)を構築して参りました。弊社はお客様にとっての利便性と最先端なサービスを兼ね備えたプラットホームでありたいと考えています。
3.提案型コンサルティング
相続関連業務における申告・対策の答え(提案)は、決して1つとは限りません。むしろ複数あると言っても過言ではありません。 弊社は考えられる複数の答えを、余すことなくオープンにして検討していきます。 それぞれの特徴やメリット・デメリット、さらに税務上のリスクをシュミレーションして、お客様の納得できる提案を徹底的に作り上げていきます。

業務案内
まずはお気軽にお電話ください。
専門の相談員が初回の無料相談(60分)でわかりやすくご説明させて頂きます。誤解の生じやすいお電話口ではなく、実際にお会いし、直接お話をした上で、明確なご返答をさせて頂きたいため、お電話でのご質問にはお答えしかねます。
- 1.まずは、お気軽にお問い合わせください
-
お電話またはメールにて、ご相談内容をお伺いし、無料相談の日程調整をさせていただきます。
【天理本社】0743-63-2361【奈良センターオフィス】0742-36-0020【大阪事務所】06-6541-6790受付時間:平日9時~19時 土曜日9時~18時 日・祝10時~17時 (一部例外日あり)
※お電話の際は、「ホームページを見た」とお伝えください。
- 2.ご予約の日時に当事務所へお越しください
-
スタッフ一同、お客様のご来所を心よりお待ちしております。 スタッフが丁寧にご案内をさせて頂きますので、お気軽にお越しください。
面談時間:平日9時~19時 ※事前予約の場合、土日祝も対応いたします。
- 3.無料相談にてお客さまのお話をお伺いさせていただきます
-
無料相談は、60~90分の目安になります。
面談担当のスタッフが、丁寧にお客さまのお話をお伺いさせていただきます。このうえで、出来るだけ丁寧に全体像や申告における注意点、手続きの流れについてご案内させていただきます。※資料などをお持ちいただくとより具体的なご相談をさせていただく事が可能です。
- 4.お手伝い内容や費用についても詳しくご説明させていただきます
-
当法人では、サポート内容も、料金も、自信をもってご案内出来る内容になっております。
どのようなサポートが可能なのか、またその料金についても説明も丁寧にさせて頂きます。 まずは、初回の無料相談へとお気軽にお越しください。
料金プラン
スタンダードプランの料金
- 相続財産評価
相続税申告 - 税務アドバイス
- 書類収集の支援
遺産分割協議書の作成
サポート内容
| 基本申告 業務 |
複数の税理士と不動産鑑定士の目を通して評価額の減額を検討します。 |
|---|---|
| あんしん 税務 サポート |
将来の節税対策、預金調査、書面添付制度の活用など。 |
| 相続 手続き サポート |
相続人確定から相続財産調査のアドバイスをいたします。 |
※ 戸籍収集や金融機関の調査などの相続手続きの事務代行は別途費用となります。
基本報酬
基本報酬(サポート料金)+個別加算報酬 の合計が報酬となります。お客様の状況にあった御見積をさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
| 財産総額 | サポート料金 |
|---|---|
| 4千万円未満 | ¥275,000 |
| 6千万円未満 | ¥385,000 |
| 8千万円未満 | ¥495,000 |
| 1億円未満 | ¥605,000 |
| 1億5千万円未満 | ¥770,000 |
| 1億8千万円未満 | ¥990,000 |
| 2億2千万円未満 | ¥1,320,000 |
| 2億5千万円未満 | ¥1,540,000 |
| 3億円未満 | ¥1,760,000 |
| 3億5千万円未満 | ¥1,980,000 |
| 4億円未満 | ¥2,200,000 |
| 5億円未満 | ¥2,420,000 |
| 5億円以上 | 別途お見積り |
※ 消費税込みの料金です。
※ 財産総額とは、借入金等の債務や葬式費用を控除する前の財産総額であり、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険金・退職手当金の非課税枠を考慮する前の金額です。また、土地の評価について広大地評価・純山林評価・不動産鑑定評価等の特殊な評価を行う場合は、それらの特殊な評価を行わない通常の評価による土地の評価額を基に計算致します
個別加算報酬
| 相続人 2名以上 |
1人増す毎に基本報酬×10% |
|---|---|
| 土地 1評価単位 につき |
27,500円〜 |
| 非上場 株式評価 1社につき |
165,000円〜 |
※ 消費税込みの料金です。
※ 申告期限3ヶ月以内・・・報酬総額×20%
基本報酬に含まれていない費用
- 不動産評価に必要な公図や謄本等の取得費用
- 訪問や不動産の現地調査の際の旅費交通費の実費
- 銀行、証券会社等の残高証明書、預金取引履歴の取得費用
- 戸籍、住民票等の取得、相続関係説明図の作成費用
- 税務調査の立会い、対応の際の報酬
- 準確定申告報酬
- 相続登記の際の登録免許税、司法書士報酬
- 土地の評価で不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬
- 弁護士報酬
- 延納申請、物納申請報酬
相続税申告における
お手伝いの流れや期間、また報酬等を
できるだけ明確にお伝えすることを
心掛けております。
ご不安なことや気になることがございましたら
お気軽に無料相談をご活用ください。
FAMILY TRUST家族信託
相続税対策と家族信託を
一緒にアドバイスできます

-
民事信託・家族信託の仕組みづくり → 初回はご相談料を頂いておりません。
-
信託契約書の作成(遺言信託のご相談)
-
信託財産に不動産がある場合の不動産登記手続き
-
信託監督人や受益者代理人への就任
-
家族信託活用後のメンテナンス
-
相続税シミュレーション及び相続税対策のアドバイス
-
相続に関する法律相談
料金プラン
信託する財産額に対する料金
| 1億円以下の部分 | 1% (3000万円以下の場合は30万円) |
|---|---|
| 1億円超 3億円以下の部分 |
0.5% |
| 3億円超 5億円以下の部分 |
0.3% |
| 5億円超 10億円以下の部分 |
0.2% |
| 10億円超の部分 | 0.1% |
※ 不動産の信託の場合には、名義変更手続きとして司法書士報酬16万5千円(税込)が必要になります。
※ 不動産の信託の場合には、別途、登録免許税が発生します。
※ 信託財産を管理する預金口座を開設する手続きを代行する場合には、別途11万円(税込)のご報酬を頂戴いたします。
信託とは

①委託者
(財産を預ける人)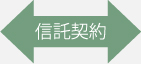

②受託者
(財産を預かる人)

③受益者
(賃料や売却収入を得る人)
その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、
その管理・処分を任せる仕組みです。
民事信託の特徴
分散した財産の名義を集める
- 目的
- 共有名義不動産対策、分散した自社株対策
- 効果
- 分割協議時において、共有財産をもめることなくスムーズに分割することが可能になる。
もう一つの財布に財産を分離する
- 目的
- 認知症対策
- 効果
- 法人を受託者になることで、永続的に財産を管理することが可能になる。
最初の意思を完結する
- 目的
- 認知症対策、遺言を撤回不能にする
- 効果
- 受託者の意思を信託契約の中ですべて完結することが可能になる。
何代も先の財産取得者を指定する
- 目的
- 財産の分散回避する
- 効果
- 財産の未分割による相続税特例非適用を回避させ、何代先まで財産の集約を可能にする。
不動産流通税の圧縮をする
- 目的
- 不動産取得税等の回避
- 効果
- 受託者へ不動産を移転する際に、不動産取得税の免税及び登録免許税の軽減を可能にする。
信託活用チェックシート
- 高齢で判断能力がなくなる心配があり、財産管理できなくなる可能性がある
- 配偶者が既に判断能力がないため将来心配
- 推定相続人の中に連絡の取れない人がいる
- 実家を売却したいが所有者の判断能力がなくなる心配がある
- 今は元気だけど、認知症になった後も子や孫に贈与を続けたい
- 親族に障害者や自立生活が困難な者がいる
- 前の配偶者の子や認知した子など相続権は持っているが相続に関係してほしくない者がいる
- 遺言を書いても遺留分請求してくると思われる者がいる
- 先祖代々の財産を直系血族のみに継がせたい
- 遺言書を書くことに抵抗がある
- 不動産が共有である、もしくはその可能性がある
- 売買で不動産の所有権を移転すると多額の流通税がかかる
- 会社の株が共有になっている、もしくはその可能性がある
- 会社を経営していて後継者問題を抱えている
GIFT相続・贈与
相続・贈与に関する
様々な知識

1.申告期限 (相続税法 第27条①)
2.遺言
尚、自筆証書遺言書は住所地の家庭裁判所で検認手続きを経て、さらに封印された遺言書は開封をお願い致します。
3.相続の放棄 (民法 第938条)
相続放棄をされた場合には、原則として債務控除の適用はありません。
また、生命保険金及び退職金の非課税の特例は受けられません。
遺贈により取得した財産がある場合でも、相次相続控除の適用はありません。
4.生前贈与加算 (相続税法 第19条)
対象となる過去3年分の贈与申告書の控えをご提示下さい。
5.配偶者の税額軽減 (相続税法 第19条の2)
ただし、申告期限までに遺産分割の確定していない財産については、この制度の適用はありません。
また、未分割であっても、その後相続税の申告期限から3年以内に遺産分割の全部が終了したときにはこの制度が適用されます。この場合には遺産分割終了の日から4ヶ月以内に既に納付した税額の還付請求をすることになりますので、当事務所まで連絡をお願い致します。
6.相次相続控除 (相続税法 第20条)
被相続人が10年以内に相続により財産を取得し、納税されているようでしたら、そのときの相続税の申告書あるいは修正申告書を提示して下さい。
7.障害者控除 (相続税法 第19条の4)
8.小規模宅地の評価減の特例 (措置法 第69条の3)
尚、この制度は遺産分割が成立していないと適用を受けることができませんのでご注意下さい。
9.農地等の納税猶予 (措置法 第70条の6)
この制度の適用を受けるためには、その対象となる農地について申告期限までに農業相続人が遺産分割により取得していること、申告期限までに猶予される相続税に相当する担保を提供することなどのいくつかの要件を満たすことが必要です。また、適用を受けた後につきましても、譲渡した場合には本制度の適用が取り消される場合もありますので、相続財産のうちに農地等がある場合には、事前にご相談下さいますようお願い致します。
10.延納と物納 (相続税法 第38条、第41条)
(2)物納
相続財産のほとんどが不動産であるなどの理由により、相続税を金銭で納付することが困難な場合には、相続財産である国債や不動産などにより物納することができます。
上記の申請はいずれも申告期限または納期限までに申請することが必要となります。
11.連帯納付義務 (相続税法34条)
相続人が複数いる場合においてそのうちの一人でも納税をしなかった場合には、互いに相続により受けた利益の価額を限度として連帯納付の義務を負うこととされています。
(2)被相続人の相続税の連帯納付義務
被相続人が以前発生した相続について納付すべきであった相続税を未納付のまま死亡した場合は、その被相続人が未納にしていた相続税額について、相続人が相続により受けた利益の額を限度として互いに連帯納付の義務を負うこととされています。
(3)相続により取得した財産が贈与された場合
相続により財産を取得した相続人から相続により取得した財産の贈与を受けた場合には、その贈与を受けた者は、その贈与をした相続人が納めるべき相続税額のうち贈与を受けた財産の価額に対応する金額を限度として、連帯納付の義務を負うこととされています。
12.未分割の場合 (相続税法 第55条)
13.被相続人の所得税の確定申告 (所得税法 第124条)
自社株対策
-
将来の相続を考えて、後継者に確実に事業承継する方法はないだろうか?
-
事業承継の時期はいつが良いだろうか?
-
株価が高くなる前に後継者に自社株を移転しておきたい。
-
相続人でない親族に財産を遺贈したい。
-
名義借りの株式があるから今のうちに整理しておきたい。
-
株価の算定または予想をします。
-
自社株の売買や贈与の契約書を作成します。
-
自社株の売買や贈与に伴う税務申告のお手伝いをします。
遺言書作成
相続が発生した時に遺言書がない場合には相続人間で遺産分割をする必要があります。
相続人間で話し合いがつかないと税金面や事業などの経営面でマイナスになる心配があります。 こんな時は、遺言書を遺すことをおすすめします。
- 親族間でもめないように遺言書を遺しておきたい。
- 家業を特定の者に継いでもらいたい。
- 面倒をみてくれたあの方に財産を遺贈したい。
- 相続人でない親族に財産を遺贈したい。
- 子供がいない夫婦なので将来の相続が心配。
お手伝いの流れ
(公正証書遺言を作成するまで)
生前対策
通常は、相続発生後に行う相続税の申告業務のうち、相続発生前に半分の業務(主に土地評価及び税務調査対策)を行うものです。
これにより、不安の解消、相続税節税、納税資金の確保が出来ます。
-
多く土地をお持ちで、将来の相続税の納税資金に不安がある方
-
近い将来の相続が心配で、生前でないと出来ない対策をしておきたい方
-
遺産分割や納税資金等の検討に余裕を持って行いたい方
-
親族名義の財産など、税務調査時に問題になりそうな事項を事前に把握し、可能な限りの対策をしておきたい方
-
通常は相続人の負担となる相続税の申告費用の一部や測量費用などを予定相続財産から減らすことで、相続税の節税になります。
-
税務調査時に問題になりそうな事項をピックアップし、問題の把握と解消ができます。
-
相続発生前に、正確な相続税額の計算ができ、適切な納税対策や節税対策を行うことが出来ます。
-
相続が発生した後に時間のかかる分割協議や納税方針の決定、納税資金確保のための土地売却などに余裕を持って進めることが出来ます。
-
相続発生に伴う不安・疑問を、全般的に解消することができます。
不動産売買・贈与
-
親族間で土地や建物の売買を考えているが、いくらで売買したら問題がないのだろうか?
-
借入金とともに賃貸不動産を引継ぎたいが、どのような税金の問題があるのだろうか?
-
親族所有の借入金がある賃貸不動産を借り替えて名義変更したいが、売買価格や税金の問題があるのだろうか?
-
不動産の贈与を考えているが、贈与税の負担を少なくする方法はないだろうか?
-
相続時精算課税制度を利用するケースの対策を教えて欲しい。
-
適正な売買価格や不動産の評価額を算定します。
-
法的に有効な取引とするために、売買契約書等の作成をします。
-
売買や贈与に伴う税務申告のお手伝いをします。
不動産交換
-
親族間で共有になっている土地を単独所有にしたい。
-
お互いに所有している、別の場所に所在する土地を交換したい。
-
地主様と借地人様が双方で底地と借地権を交換したい。
-
将来の相続税の納税のために、親族の所有している土地と交換したい。
-
交換する価格を算定します。
-
法的に有効な取引とするために、交換契約書の作成をします。
-
税務の特例(交換の特例)適用のために申告書類の作成をします。
